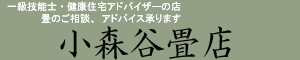そのままの糸
「表替え」や「裏返し」をする時には、前回畳を縫っていた糸はいらなくなります。
「いらなくなった糸」は邪魔ですから、本来は抜き取ります。
しかし、中には「いらなくなった糸」をそのままにして、その上から縫ってしまう畳屋(?)
もいるようです。
写真は現在縫ってあった糸を抜いたところですが、その下にはさらに糸が・・・ |  |
|
そのままの糸2
すべて糸を抜くと、これだけの「いらない糸」が溜まっていました。
これは「畳の長手側」片方だけの「いらない糸」です。
これを繰り返すと、どれだけの糸が溜まっていくでしょう。
不要な物は取り除かなければいけません。
|  |
|
切ってはいけないところまで・・・
畳を解く時は、糸だけを切るのが当たり前です。
この写真を見ると、糸だけではなく、畳そのものまで切り込みが入っています。
どの段階で(何回目の畳替えで)切られたものかは分かりませんが、畳裏の保護材である
「裏シート」はおろか、畳床の縫い糸まで切ってしまっています。 |  |
|
切ってはいけないところまで・・・2
現在縫ってあった糸を解いたところです。
前回の糸がそのままになっていると共に、切られてしまった「裏シート」と
「畳床の縫い糸」が良く分かります。
これでは畳の寿命にまで影響してしまいます。 |  |
|
縁が何重にも・・・
畳の側面部分ですが、縁が何枚も重なっています。
畳替えをする時には、古い「畳縁」と「それを縫っていた糸」は必要無くなるのですが・・・
古い糸を抜いたり、古い縁を外すという事がそんなに面倒なのでしょうか。 |  |
|
側面をタッカーで・・・
縁の側面をタッカーでとめていますが、これでは縁がつれません。
畳を使用しているうちに、縁がだぶついてきますよ。
敷いてしまえば見えない、と言えばそれまでですが。。。 |  |
|
タッカーで縁を・・・
鉄骨や鉄筋造りの住宅には良くある、柱の切欠け部分です。
足当たりが無い部分と言えばそれまでですが、家具などで縁を引っ掛けると抜けてしまいます。
このような場所には機械が入らず、縫えないからでしょうが・・・ |  |
|
手で縫えば良いのです。
機械に入らないからと言って、縫えないわけではありません。
機械が入らなくとも、手で縫えば良いだけの事です。
畳に対して、技術を惜しむ理由は何もありません。 |  |
|
タッカー止工法〈平刺し 1〉
写真でお分かりになるでしょうか? 柱型の切り欠け部分ならまだしも、すべての「縁」を
縫う事無くタッカー止してあります。
指で引っかけると、簡単に写真のように持ち上がってしまいました。
危ないですね。 |  |
|
タッカー止工法〈平刺し 2〉
縁を開いたところです。 すべてタッカー止で、一切縫うことはしていません。
畳床ごと縫って仕上げるのが「普通」であり、畳が膨れるのを抑え、型崩れを防ぐことにもなります。
写真のような状態では、そのような効果はありません。 畳を使用すればするほど型崩れを起こして
しまいます。 特許工法と書いてありますが… |  |
|
タッカー止工法〈かまち止め 1〉
裏側の畳表を止めている部分です。 畳表の経糸末端の解れ止めをしていないため、
畳表が緩んでしまっています。
この部分も縫っていないため、膨れや型崩れの原因にもなります。 |  |
|
タッカー止工法〈かまち止め 2〉
畳表をはがしたところですが、以前に縫ってあった糸がそのままになっています。
この工法の前に畳替えをした畳屋も糸を抜かずにそのまま施工したようです。
今回、不必要な糸はすべて抜き取りました。 |  |
|
| |
|